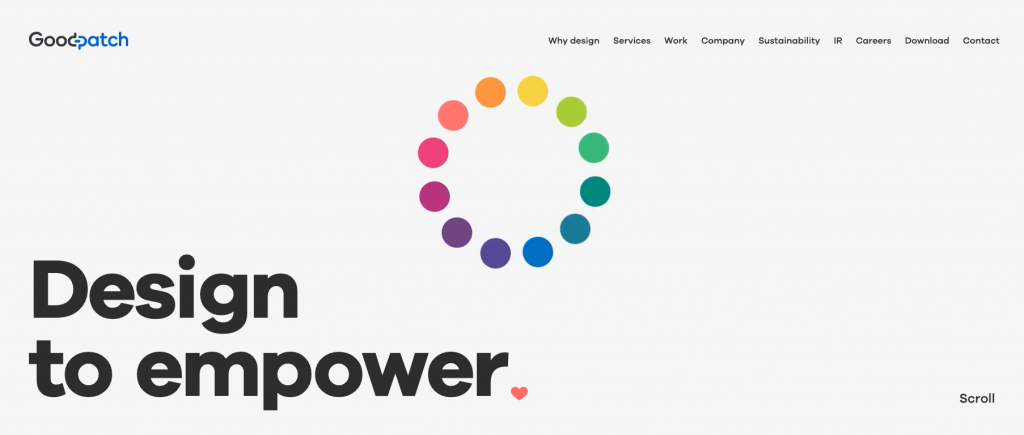LINE広告は、国内で圧倒的なシェアを誇るメッセージアプリ「LINE」を活用した広告手法です。スマートフォンを日常的に使用するユーザーにダイレクトにリーチできるため、高い効果が期待できます。本記事では、LINE広告の基本的な仕組みから、広告代行を利用するメリット、信頼できるLINE広告代行会社を14社厳選して紹介。これからLINE広告を活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
LINE広告とは? LINE広告は、日本で広く利用されているコミュニケーションアプリ「LINE」を活用したデジタル広告です。LINEのユーザー基盤を活用し、多種多様な広告フォーマットとターゲティング機能を用いて広告を配信できます。
LINE広告の特徴は、プラットフォームの多機能性にあります。LINE広告は、LINEアプリ内のタイムラインやトーク一覧、LINE NEWS、LINEマンガなど、様々な場所に表示される仕組みがあるため、ユーザーの目に自然に広告を届けることが可能です。
広告フォーマットとしては、バナー広告、動画広告、カルーセル広告など、多彩な選択肢があり、キャンペーンの目的やターゲットに応じて最適な形を選ぶことができるのも魅力です。
複数あるLINE広告の配信面と対応フォーマット LINE広告では、LINEアプリ内および外部の提携アプリに対して、多様な広告フォーマットを使って配信が可能です。配信面によって表示される場所やターゲット、訴求方法が異なるため、自社の目的に合ったメディアとクリエイティブを選ぶことが重要です。
以下に主要な配信面と、代表的なフォーマットをまとめています。
主な配信面と特徴 出典:https://www.lycbiz.com/jp/column/line-ads/technique/20191024/ トークリスト上部 LINEアプリ内でもっとも視認性が高い場所に配信されます。静止画・動画いずれも対応し、幅広い層にリーチが可能です。
LINE VOOM ショート動画や投稿が表示されるフィード。若年層や動画視聴ユーザーへのアプローチに適しています。
LINE NEWS ニュース記事の間に表示されます。情報感度が高いユーザーに対して効果的です。
LINEファミリーアプリ(LINEマンガ、LINEショッピングなど) 各アプリのユーザー層に合わせたターゲティングが可能です。特定商材に特化した訴求がしやすいのが特徴。
対応フォーマットとサイズ一覧 Card(静止画) ■ 形式:PNG/JPEG
■ サイズ・比率:1200×628px
■ 対応面:すべての配信面
■ 特徴:基本となるフォーマットで使い勝手が高い
Square(静止画) ■ 形式:PNG/JPEG
■ サイズ・比率:1080×1080px
■ 対応面:トークリスト以外
■ 特徴:表示領域が広く、視認性に優れる
Carousel(静止画) ■ 形式:PNG/JPEG
■ サイズ・比率:1080×1080px ×最大10枚
■ 対応面:LINE VOOM・NEWSなど
■ 特徴:商品のバリエーション訴求に適している
画像(小) ■ 形式:PNG/JPEG
■ サイズ・比率:600×400px
■ 対応面:トークリスト・LINE NEWSなど
■ 特徴:軽量かつ量産しやすい。初期制作におすすめ
画像(アニメーション) ■ 形式:PNG (APNG)
■ サイズ・比率:600×400px
■ 対応面:トークリスト
■ 特徴:トークリストの静止画より目を引きやすい。
Card(動画) ■ 形式:mp4/MOV
■ サイズ・比率:16:9(例:1920×1080px)
■ 対応面:トークリスト、LINEオープンチャット以外の配信面
■ 特徴:高い訴求力。動的なアピールが可能
Square(動画) ■ 形式:mp4/MOV
■ サイズ・比率:1:1(例:1080×1080px)
■ 対応面:トークリスト、LINEマイカード、LINEオープンチャット以外の配信面
■ 特徴:幅広い配信面に対応する動画フォーマット
Vertical(動画) ■ 形式:mp4/MOV
■ サイズ・比率:9:16(例:1080×1920px)
■ 対応面:LINE VOOM、LINE NEW、LINEファミリー、広告ネットワークなど
■ 特徴:スマホに最適な縦型動画で没入感を演出可能
このように、LINE広告では様々なフォーマットがあります。初めてLINE広告を運用する場合、以下の3つのフォーマットを用意しておくと、多くの配信面に対応でき、効果も得やすいとされています。
画像(小):トークリストに掲載されやすく、表示回数が多い 画像(アニメーション):動きがあり、目を引きやすい Square(静止画):配信面が広く、汎用性が高い 配信面や目的に応じて、静止画・動画・カルーセルなど複数のクリエイティブを併用することで、LINE広告の効果を最大限に引き出すことができます。
LINE広告の課金方式 LINE広告を掲載するには、当然ですが費用がかかります。ここでは、LINE広告の主な課金方式について解説します。
インプレッション課金方式 インプレッション課金方式(CPM)は、広告がユーザーに表示されるたびに課金される仕組みです。CPMは「Cost Per Mille」の略で、広告が1,000回表示されるごとに発生するコストを基準に必要な費用が計算されます。
インプレッション課金では、「新商品を多くの人に知ってもらいたい」「イベントの開催を広く告知したい」といったケースで効果的です。ターゲティングを細かく設定することで、限られた予算でも効率的にリーチが広げられます。
クリック課金方式 クリック課金方式(CPC)は、広告がクリックされた際に課金される仕組みです。CPCは「Cost Per Click」の略で、広告がどれだけクリックされたかに基づいて費用が発生します。
クリックされなければ費用は発生しないため、コストパフォーマンスを重視する企業に人気があります。また、Webサイトへの誘導やLP(ランディングページ)でのコンバージョン獲得が目的の広告に最適です。
友達追加ごとに課金 友達追加ごとに課金される方式は、LINE公式アカウントの友達数を増やすのが目的の場合におすすめの課金方式です。広告を通じてLINE公式アカウントに新しい友達が追加されるたびに課金されます。
この形式は、LINE広告の独自性のひとつであり、初回接点だけでなく中長期的なコミュニケーション設計を重視するマーケティングにも向いています。
LINE広告代行とは? LINE広告代行とは、LINE広告の専門知識と実績を持つ外部パートナーに、広告運用の一連の業務を委託できるサービスです。自社のマーケティングリソースを圧迫せず、効率的に成果を上げたい企業にとって、有力な選択肢となります。
特に、LINE広告は、配信面の多さやターゲティング設定の複雑さ、クリエイティブの種類など、適切に運用するには専門的な知見が求められます。こうした背景から、社内での内製化には限界を感じている企業も少なくありません。
LINE代行会社に任せられる主な業務 以下のような業務を、すべてワンストップで外注できます。
■ 広告戦略の立案(目的に応じた媒体・ターゲット・KPIの設計)
■ アカウント設計および配信設定(LINE VOOM、トークリストなど配信面の最適化)
■ 広告クリエイティブの制作(静止画・動画・カルーセルなど)
■ 効果測定・レポートの作成(インプレッション、クリック率、CPAなどの分析)
■ 継続的な運用改善提案(クリエイティブABテスト、ターゲット調整、入札最適化)
これらをプロに任せることで、社内のリソースを割くことなく、広告効果の最大化が図れます。中でも「LINE広告を導入したいが初期設計から任せたい」「運用中の広告成果が頭打ちになっている」といった企業にとって、LINE広告代行は最適な打ち手といえるでしょう。
LINE広告代行会社を利用するメリット LINE広告代行会社を利用するメリットは、主に5つあります。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
リソースを本業に割ける 広告運用には戦略設計からクリエイティブ作成、ターゲティングの設定、効果測定まで、多くの手間がかかります。LINE広告代行会社に任せることで、自社のリソースを本業に専念させることが可能となります。
特に、リソースの限られた中小企業やスタートアップ企業にとっては、大きなメリットです。
費用対効果が高い LINE広告代行会社は豊富な経験と知識を活かして、広告費を無駄にすることなく、効果を引き出すことが可能です。例えば、ターゲティングの最適化やクリエイティブの改善を通じて、限られた予算でより高い成果を実現できます。
また、分析したデータを基に改善策を実施して、広告運用の効率をさらに高められる点も特徴です。
プロに分析や改善を任せられる 広告運用は一度設定すれば終わりではなく、継続的な分析と改善が不可欠です。LINE広告代行会社は専用ツールや独自のノウハウを駆使して、データを分析し、改善を行ってくれます。常に高い効果を得やすいのもLINE広告代行会社を利用するメリットです。
最新のトレンドに対応してくれる LINE広告は新しいフォーマットや機能が次々と登場します。LINE広告代行会社は常に最新の広告トレンドやプラットフォームのアップデート内容を把握し、それを活用した最適な運用を行います。
常に最適な広告配信が可能な点も、LINE広告代行会社を利用するメリットです。
競合相手との競争に勝ちやすくなる 専門知識を持つLINE広告代行会社は、競合の動向を踏まえた戦略立案が得意です。市場やターゲット層に適した広告戦略を展開することで、他社との差別化を図れます。結果として、競争の激しい市場でも効果的にユーザーを引きつけることが可能です。
LINE広告の予算 LINE広告には固定の料金メニューがなく、広告主が自由に予算を設定できます。広告予算は「目標CPA」(1件のコンバージョンにかける許容費用)と「目標コンバージョン数」(獲得したい成果数)を基に以下の計算式で算出します。
例えば、1件3,000円で月400件の成果を目指す場合、予算は月120万円となります。少額から利用可能ですが、一定の予算があったほうが効果が出やすい傾向があります。目安としては、月30万円以上の予算を3ヵ月以上継続するのがおすすめです。
「友だち追加」に特化した広告は獲得単価が200円~300円程度と低コストで運用できるため、月10万円の予算でも高い効果が得られる可能性があります。
LINE代行会社に支払う費用の目安 LINE代行会社に依頼する場合、広告費に加えて「運用代行費」や「初期設定費」が発生する場合があります。
■ 広告費(出稿費):月10~50万円~/LINEへ直接支払う配信費用
■ 運用代行費:広告費の20%前後または月額10〜30万円/戦略立案・運用・レポート含む
■ 初期設定費: 5万〜20万円(初回のみ)/アカウント設計・タグ設定・ヒアリング等
代行費用は会社によって「定額制」「従量課金制(%)」「成功報酬制」など異なります。サービス内容とあわせて確認するといいでしょう。
LINE広告代行会社の選び方 LINE広告代行会社を選ぶ際は、5つのポイントが重要です。ここでは、その5つのポイントについて詳しく解説します。
実績の豊富さ LINE広告代行会社の実績は、LINE広告運用の成果に直結します。LINE広告の運用経験が豊富か、同じ業種や商材で成功事例があるかを調べるとよいでしょう。また、LINE公式認定パートナーの資格を持つ会社は、LINE広告に関する深い知識と運用ノウハウが期待できます。
サポート体制 運用開始後も継続的にサポートが受けられるかを確認してください。例えば、広告の改善提案や定期的な報告があるかどうかがポイントです。初回の相談やヒアリングで、どれだけ具体的で現実的なアドバイスをしてくれるかを確認しましょう。
料金体系のわかりやすさ LINE広告代行会社によって料金体系は異なるため、事前にどのような費用が発生するのかを明確にしておく必要があります。広告運用費用のほかに、手数料や追加料金が発生する場合もあるため、契約内容をしっかり確認してください。
また、提示された費用が成果に見合うかどうか、他社と比較してコストパフォーマンスが良いかも判断基準に含めると安心です。
LINE認定パートナーか LINE広告代行会社を選ぶ際にひとつの指標となるのが、LINE社による「認定パートナー制度」です。これは、LINEが定める一定の基準(広告運用実績や体制、クリエイティブの品質など)を満たした企業に与えられる公式の認定制度であり、認定企業には「Technology Partner」「Ads Operation Partner」などの区分があります。
認定パートナーであれば、LINE社との連携体制が強く、広告配信に関する最新情報や機能アップデートへの対応も迅速です。また、LINE広告の仕様変更が頻繁にある中で、そうした情報に遅れず対応してくれる点は、企業側にとって大きな安心材料となります。
自社の業界に強い会社であるか LINE広告は特性上、BtoC向け商材との相性が良い一方で、業種や商材によってユーザーの行動特性やKPIも異なります。そのため、過去に自社と類似する業界やターゲット層での運用実績があるかどうかは、成果を出すうえで非常に重要です。
業界特有の商流や意思決定プロセスを理解した上で、適切な媒体設計・訴求軸を提案してくれる会社であれば、初期フェーズから効率的な運用が期待できるでしょう。
おすすめLINE広告代行会社 14 選 LINE広告代行会社は数多く存在します。ここでは、その中でも特におすすめなLINE広告代行会社14選を紹介します。
1. 株式会社BLAM (ブラム) 出典:https://blam.co.jp/ 『株式会社BLAM』は、独自のPjTO(プロジェクトチーム・オプティマイゼーション)マーケティングの手法を軸に、戦略コンサルティングからWeb広告・クリエイティブ制作・CRMまで、幅広いマーケティング課題を解決している会社です。
LINE広告代行においても、企業ごとの目標や予算に応じて柔軟にチームを組成し、最適なプランで運用支援を実施。さらに、国内最大級のマーケティング領域特化型複業マッチングサービス「カイコク
【 カイコク 】
会社名 株式会社BLAM(ブラム) ホームページ https://blam.co.jp/ 所在地 東京都品川区西五反田7丁目7−7SGスクエア8F 事業内容 ■ クラウド型マーケティングDX支援サービス■ マーケティングDX事業■ 研修・人材紹介事業
2. サイバーホルン株式会社 出典:https://cyberhorn.co.jp/ サイバーホルン株式会社の特徴は、柔軟な運用体制と専門性の高さにあります。LINE広告運用を専門とする担当者が日次レポートを提供し、契約条件に縛られない柔軟な対応を行っています。小規模な運用から100万円以上の運用代行まで、幅広く対応可能な点も魅力です。
また、クリエイティブ制作にも強みがあり、商材や業界ごとの訴求ポイントを反映した静止画・動画の制作にも対応。中小企業から上場企業まで幅広い支援実績があり、LINE広告を通じて事業成長を加速させたい企業にとって信頼できるパートナーといえるでしょう。
会社名 サイバーホルン株式会社 ホームページ https://www.cyberhorn.co.jp 所在地 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 人形町ビル3F 特徴 SNS広告に特化。小規模から大型プロジェクトまで柔軟に対応。 費用 初期費用:0円
3. 株式会社電通デジタル 出典:https://www.dentsudigital.co.jp/ 株式会社電通デジタルは、LINE広告分野での確かな実績と最新技術を駆使した運用が魅力です。「LINE Planning Contest 2022」で「Gold」に認定されるなど、認定パートナーとして高い評価を受けています。AIを活用したクリエイティブ制作や独自のデータ・ツールによる運用で、優れた広告効果を実現しています。
大企業やナショナルクライアントの実績が豊富で、戦略性とスケールの両立を求める企業に適したパートナーです。
4. 株式会社オプト 出典:https://www.opt.ne.jp/ 株式会社オプトは、「動画制作・運用に強みを持ち、LINE広告における動画配信においても高い実績を有しています。動画を活用した広告を希望する方にとっておすすめの広告代理店です。また、API配信ツールなどの販促ツールで「LINE Biz Partner Program」の「Sales Partner」として表彰されるなど、LINE広告分野での実績も豊富です。
LINEを含む各種SNSや動画広告、EC領域など多彩なチャネルとの連携実績も豊富で、複数施策を統合的に運用したい企業にも適したパートナーです。
5. 株式会社博報堂 出典:https://www.hakuhodody-media.co.jp/ 株式会社博報堂は、2025年4月にグループ内の株式会社博報堂DYメディアパートナーズを吸収統合し、統合型マーケティング支援体制をさらに強化しました。これにより、マスメディアとデジタルの両軸を高度に融合させたフルファネル型支援をワンストップで提供できる体制が整備されています。
LINE広告代行領域においても、旧DYメディアパートナーズ時代から培ってきた運用実績と専門性を引き継ぎ、LINEヤフーの「Sales Partner Premier」といった認定資格を保持。多層的な広告・販促支援が可能で、大規模な統合プロモーションを展開する企業にとって、信頼性の高いパートナーといえるでしょう。
6. 株式会社DYM 出典:https://dym.asia/ 株式会社DYMは、Webマーケティング全般に対応する広告代理店で、LINE広告を含む幅広いマーケティング戦略の見直しをサポートします。2017年からLINE広告の運用代行を行っており、豊富な広告運用ノウハウを活かして効果的な施策を実施可能です。
2024年度上半期には「LINEヤフー Partner Program」において最上位の Sales Partner Premier に認定されました。また、薬機法に気を付けたコンテンツ制作や運用代行をおこなってくれるため、医療系や美容系の企業にも適したパートナーです。
会社名 株式会社DYM ホームページ https://dym.asia/ 所在地 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー 10階 特徴 Sales Partner Premier認定、プランや料金形態を柔軟に提案してくれる。 費用 問い合わせ
7. 株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ 出典:https://www.pbmp.co.jp/ PLAN-Bマーケティングパートナーズは、大規模アカウントと中小規模アカウントの運用経験を活かし、幅広い規模に対応できるのが特徴のコンサルティング会社です。KPI達成率やお客様満足度を重視し、顧客の売上への貢献度を追求しているのも強みです。
また、Google Premiere PartnerやYahoo!セールスパートナーなど複数の認定を取得し、信頼性の高い運用体制を構築。マーケティング全体を戦略的に見直したい企業にとって、心強いパートナーです。
会社名 株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ ホームページ https://www.pbmp.co.jp/ 所在地 東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階 特徴 LINE広告代行に豊富な実績があり、大規模〜中小アカウント対応。 費用 問い合わせ
8. 株式会社Enigol 出典:https://enigol.com/ Enigolは、デジタル時代におけるカスタマー・エクスペリエンス(CX)をリードするコンサルティング会社です。LINE広告代理店としての強みは、LINE広告に特化した専門家が運用を行う点、長期的に安定した集客を実現する点、そしてコンサルティングから運用まで一貫して対応できる点が特徴です。
豊富なノウハウと独自運用ロジックにより、長期的に安定した集客と費用対効果の向上を実現します。
会社名 株式会社Enigol ホームページ https://enigol.com/ 所在地 東京都港区北青山2丁目12-8 BIZ SMART235 特徴 LINE広告専門のプロが運用。安定した長期的な集客に期待できる。 費用 月額広告費の20%
9. 株式会社Epace 出典:https://e-pace.co.jp/ Epaceは、事業コンサル、Webマーケティング、クリエイティブ制作など多岐にわたる事業を展開しており、顧客の課題や予算に合わせてオーダーメイド型のプランを提案します。顧客の事業領域に精通した運用者が担当し、「認知獲得」や「売上向上」など、顧客の目的に合わせた柔軟な運用が可能な点が特徴です。
LINE広告代行では「LINE公式アカウント運用」や「友だち追加施策」にも対応するほか、社内スタッフへの内製化支援もセットで提供しています。
会社名 株式会社Epace ホームページ https://e-pace.co.jp/ 所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1住友不動産大崎ガーデンタワー9階 特徴 LINE広告代行(配信設計・友だち追加・PDCA支援)と広告内製化支援まで一貫提供 費用 問い合わせ
10. 株式会社グラッドキューブ 出典:https://corp.glad-cube.com/ グラッドキューブは、広告運用代行をはじめ、WEBサイトの制作・解析・コンサルティングを行っており、SaaS事業として自社開発サイト解析ツールの「SiTest」やページスピード高速化ツール「FasTest」なども展開しています。LINE広告運用専門チームによる対応が可能であり、広告主向けアンケートでもサポートの満足度が高評価を得ています。
LINE広告では、配信設定やクリエイティブ制作、PDCA改善を含む包括的運用を代行し、コミュニケーションを大切にした丁寧なサポートも魅力です 。
会社名 株式会社グラッドキューブ ホームページ https://corp.glad-cube.com/ 所在地 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル 8F 特徴 LINE広告と自社解析ツール「SiTest」による広告+サイト改善一体支援。 費用 広告費:50万円以上代行費用:広告費の20%
11. 株式会社サイバーエージェント 出典:https://www.cyberagent.co.jp/ 株式会社サイバーエージェントは、インターネット広告領域で圧倒的な実績を誇る総合的なマーケティング企業です。「LINEヤフー Partner Program」のSales Partner Premier に3期連続で認定され、さらに業界内で最上位のTop of Sales Partnerも取得(2024年上半期〜2025年上半期連続)しており、その運用力と実績が高く評価されています。
また、LINE広告代行においては、「CX Partner」にも認定され、配信戦略設計、AIやデータ分析を用いたターゲティング、クリエイティブ制作、そしてLINE公式アカウント連携によるCRM施策までワンストップで提供。大規模キャンペーンやブランドプロモーションにも適したLINE広告運用パートナーといえるでしょう。
会社名 株式会社サイバーエージェント ホームページ https://www.cyberagent.co.jp/ 所在地 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers 特徴 LINE広告「Sales Partner Premier」認定3期連続+Top of Sales Partner取得。 費用 問い合わせ
12. デジタルアスリート株式会社 出典:https://ppc-master.jp/ デジタルアスリート株式会社は、広告運用・LP・動画制作・内製化支援を一貫して提供するデジタルマーケティング支援企業です。LINE広告代行では、1,800社以上の広告運用経験を活かし、配信設定からクリエイティブ制作、友だち追加施策、数値分析・改善までワンストップで対応します。
SNS広告に特化した経験豊富なコピーライターが常駐しており、共感性の高い広告文とCVにつながるクリエイティブを制作し、LINE特有のユーザー特性に合わせた精度の高い配信が可能です。さらにFacebookやX(旧Twitter)などのSNS広告と組み合わせた多面的な運用も得意としており、広告成果の最大化を図れます。
会社名 デジタルアスリート株式会社 ホームページ https://ppc-master.jp/ 所在地 東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビルディング4階 特徴 1,800社以上の支援実績。LINE広告専任ライターが常駐。 費用 問い合わせ
13. 株式会社フルスピード 出典:https://www.fullspeed.co.jp/ 株式会社フルスピードは、LINE社から認定を受けた広告代理店で、LINE広告における豊富な実績を有しています。同社では、LINE広告の出稿だけでなく、LINE公式アカウントの開設・設計・運用、分析・改善提案まで一気通貫で対応。ターゲット層や目的に応じた広告運用戦略を立案し、配信設計、クリエイティブ制作、効果測定レポートまで丁寧にサポートします。
社内で撮影・編集を完結できる体制も整っており、スピード感のある改善提案が可能です。広告運用後の「友だち追加数の増加」や「CV(コンバージョン)数の改善」など、成果に直結する支援が強みです。
会社名 株式会社フルスピード ホームページ https://www.fullspeed.co.jp/ 所在地 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー8F 特徴 LINE社認定代理店。SNS広告運用1,000件超えで、クリエイティブ制作〜運用一括支援。 費用 カスタマイズプラン:月額30万円~
14. 株式会社ユニアド 出典:https://www.uniad.co.jp/ 株式会社ユニアドは、LINE広告運用代行を含む多様な運用型広告サービスを提供するデジタル広告の専門集団です。ヒアリングを重視し、アカウント設計、配信戦略、クリエイティブ制作、効果測定・レポートまで一気通貫で支援します。
運用担当者だけでなくクリエイティブ担当者もミーティングに参加、認識を共有し成果最大化を目指します。また、広告運用を内製化できるサポートにも対応。Google・Yahoo!などの正規代理店で、LINEヤフーの「Sales Partner」認定も取得しており、多くのLINEユーザーにもリーチ可能な広告配信設計が強みです。
会社名 株式会社ユニアド ホームページ https://www.uniad.co.jp/ 所在地 東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork 日テレ四谷ビル 6F 特徴 運用型広告専門。ヒアリング重視・定例ミーティング・内製化支援対応。 費用 運用費の20%最低出稿金額、最低契約期間もなし
LINE広告代行会社を有効活用して広告効果を最大化しよう LINE広告を活用することで、ターゲットとなるユーザーに直接アプローチでき、費用対効果の高いプロモーションが可能です。しかし、運用には専門的な知識や時間が必要なため、LINE広告代行サービスを活用しましょう。
代行サービスを活用すれば、プロの手による分析や改善を通じて、高い広告効果を期待でき、競争の激しい市場でも優位に立つことができます。自社に最適なサービスを選び、LINE広告を効果的に活用して、ビジネスの拡大を目指しましょう。
▼こちらの記事もあわせて読む